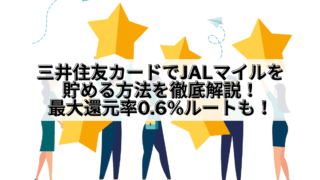老後の資産形成のためにiDeCo(イデコ)を始めたいけど、どの金融機関を選べばいいか分からない、手続きが難しそうと感じていませんか。特に、スマートフォンでの情報収集や手続きに慣れた世代にとって、手軽さと分かりやすさは重要なポイントです。
2025年10月、大手ネット証券のSBI証券から、そんな悩みに応える新しいiDeCoサービス「SBI e-iDeCo」が開始されました。このサービスは、特に投資初心者やスマホ世代をターゲットにしており、これまでのiDeCoのイメージを覆すような手軽さが魅力です。
この記事を読めば、以下の点が分かります。
⚫︎SBI証券の新サービス「SBI e-iDeCo」の全体像
⚫︎iDeCoが持つ強力な税制メリットの基本
⚫︎従来のiDeCoプラン(セレクトプラン)との具体的な違い
⚫︎スマホで完結する具体的な申し込み手順
将来に向けた資産形成の第一歩を、この記事を読んでスムーズに踏み出しましょう。
- 【結論】SBI e-iDeCoはこんな人におすすめ!
- そもそもiDeCoとは?3つの強力な税制メリットを解説
- 2025年10月開始!SBI証券の新サービス「SBI e-iDeCo」とは?
- 【徹底比較】SBI e-iDeCoと従来のプラン(セレクトプラン)は何が違う?
- SBI e-iDeCoの5つのメリット
- 知っておきたいSBI e-iDeCoの2つのデメリット・注意点
- SBI e-iDeCoの手数料を他の金融機関と比較
- SBI e-iDeCoのおすすめ商品2選【初心者向け】
- 【スマホで簡単】SBI e-iDeCoの始め方5ステップ
- SBI e-iDeCoに関するよくある質問
- 【まとめ】スマホ世代の資産形成は「SBI e-iDeCo」から始めよう
- 関連記事
【結論】SBI e-iDeCoはこんな人におすすめ!

「SBI e-iDeCo」の詳しい解説に入る前に、結論からお伝えします。この新しいサービスは、特に以下のような方に最適です。
- iDeCoを始めたいけど、何から手をつけていいか分からない投資初心者の方
- とにかく手数料を安く抑えたい方
- たくさんの投資信託から選ぶのは難しいと感じる方
- 申し込みから運用状況の確認まで、すべてスマホで手軽に完結させたい方
もし一つでも当てはまるなら、この記事はあなたのためのものです。従来のiDeCoプランとの違いも詳しく解説するので、ぜひ最後まで読み進めてください。
そもそもiDeCoとは?3つの強力な税制メリットを解説
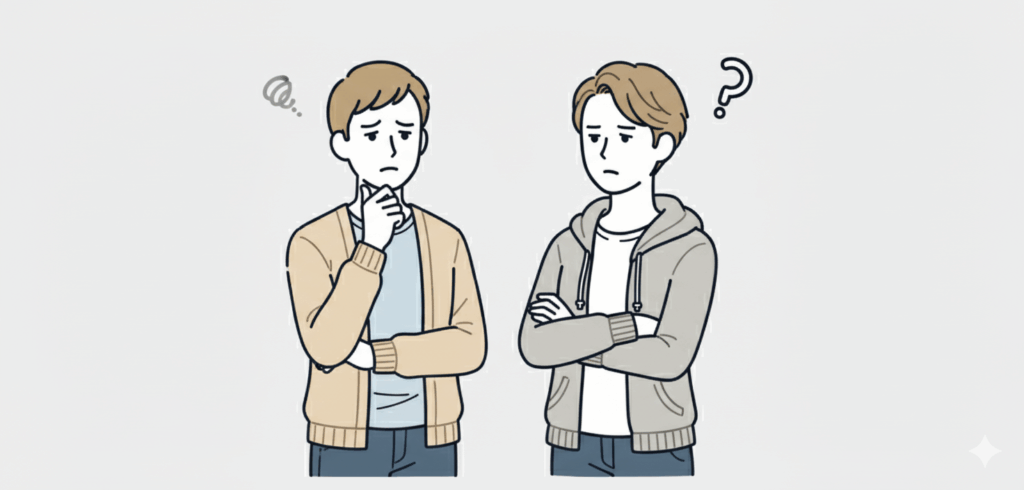
SBI e-iDeCoの解説の前に、iDeCoという制度が持つ強力な3つの税制メリットについて、簡単におさらいします。このメリットを知ることで、なぜiDeCoが「老後資金作りの最強の制度」と言われるのかが分かります。
- 掛金が全額所得控除になる(入口のメリット)毎月積み立てる掛金の全額が、その年の所得から差し引かれます。これにより、課税対象となる所得が減るため、所得税と住民税を軽減できます。例えば、毎月2万円(年間24万円)を積み立てる場合、その24万円が所得から控除されます。
- 運用益が非課税になる(運用中のメリット)通常、投資で得た利益(運用益)には約20%の税金がかかります。しかし、iDeCoの口座内で得た利益には一切税金がかかりません。利益がそのまま再投資されるため、効率的に資産を増やせます。
- 受け取るときも控除の対象になる(出口のメリット)60歳以降にiDeCoの資産を受け取る際にも、「退職所得控除」や「公的年金等控除」といった大きな控除が適用されます。これにより、受け取る際の税負担も大幅に軽減される仕組みです。
2025年10月開始!SBI証券の新サービス「SBI e-iDeCo」とは?

「SBI e-iDeCo」は、SBI証券が2025年10月3日にサービスを開始した、新しい個人型確定拠出年金(iDeCo)のプランです。これまでのSBI証券のiDeCoプラン(オリジナルプラン、セレクトプラン)とは別に、新たな選択肢として提供されます。
SBI e-iDeCoの3つの特徴
SBI e-iDeCoは、これまでのiDeCoが持つ「手続きが複雑そう」「商品選びが難しい」といったイメージを払拭するために開発されました。主な特徴は以下の3つです。
- 業界最安水準の手数料: 運営管理手数料が加入者区分にかかわらず、誰でも一律で0円です。
- 初心者向けの厳選商品: 低コストで実績のある投資信託をあらかじめ厳選。投資初心者でも迷わずに商品を選べます。
- スマホで完結する手続き: 申し込み手続きが最短5分で完了するなど、スマートフォンでの操作に最適化されています。
これらの特徴から、SBI e-iDeCoは、これまでiDeCoへの加入をためらっていた若い世代や投資初心者の方が、気軽に始めやすい設計になっています。
【徹底比較】SBI e-iDeCoと従来のプラン(セレクトプラン)は何が違う?
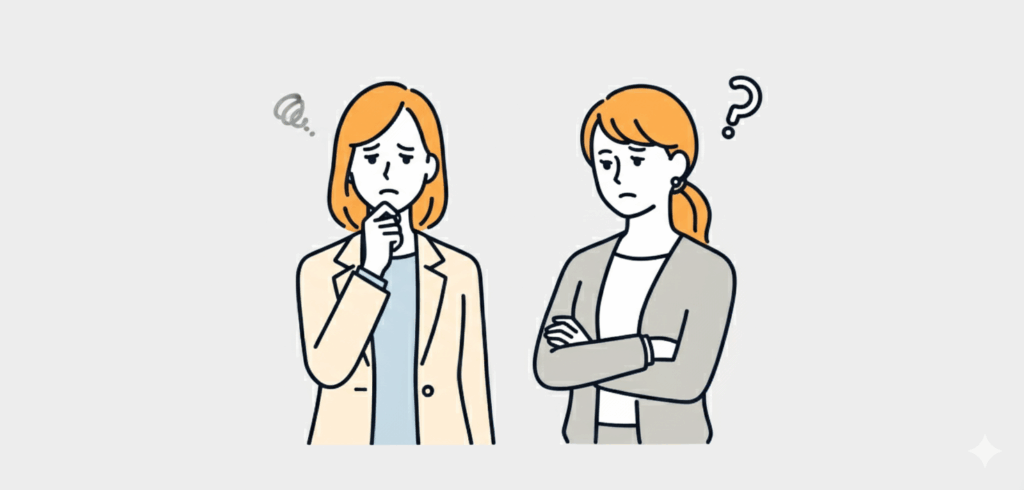
SBI証券には、以前から「セレクトプラン」という人気のiDeCoプランがあります。では、「SBI e-iDeCo」はセレクトプランと何が違うのでしょうか。ここでは、両者の違いを分かりやすく比較解説します。
比較表で見る違いのポイント
| 比較項目 | SBI e-iDeCo(新プラン) | セレクトプラン(従来プラン) |
| 主なターゲット | 投資初心者、スマホ世代 | 投資中級者〜上級者 |
| 運営管理手数料 | 0円 | 条件付きで0円 ※ |
| 商品数 | 3本 | 38本 |
| 申し込み方法 | スマホに最適化(最短5分) | Web、郵送 |
| サポート | 専用アプリ、チャット中心 | 電話、Web |
※残高50万円以上などの条件を満たした場合。満たない場合は月額330円(税込)が発生。
1. 運営管理手数料
最大の違いは「運営管理手数料」です。セレクトプランでは、預かり資産が50万円未満の場合などに月額330円(年間3,960円)の手数料が発生しました。しかし、SBI e-iDeCoでは、この手数料が資産額にかかわらず誰でも0円です。iDeCoを始めたばかりで資産が少ない時期でも、コストを気にせず運用できるのは大きなメリットです。
2. 商品ラインナップ
商品ラインナップの考え方も大きく異なります。セレクトプランが38本という豊富な選択肢を提供しているのに対し、SBI e-iDeCoは全世界株式や米国株式(S&P500)などに連動する、低コストで人気の投資信託3本に厳選しています。
これは「多くの選択肢があっても、どれを選んでいいか分からない」という投資初心者の悩みに応えるためのもの。あらかじめ実績のある商品が選ばれているため、迷うことなく資産運用をスタートできます。
3. 申し込み手続き・サポート体制
SBI e-iDeCoは、申し込み手続きをスマホで最短5分で完結できるように設計されています。本人確認もスマホのカメラ機能で行えるため、書類の郵送といった手間がかかりません。
また、運用開始後のサポートも、専用アプリやチャットが中心となり、スマホ世代が直感的に使えるインターフェースを提供しています。一方で、セレクトプランは電話でのサポートも充実しており、じっくり相談したい方に向いていると言えます。
SBI e-iDeCoの5つのメリット
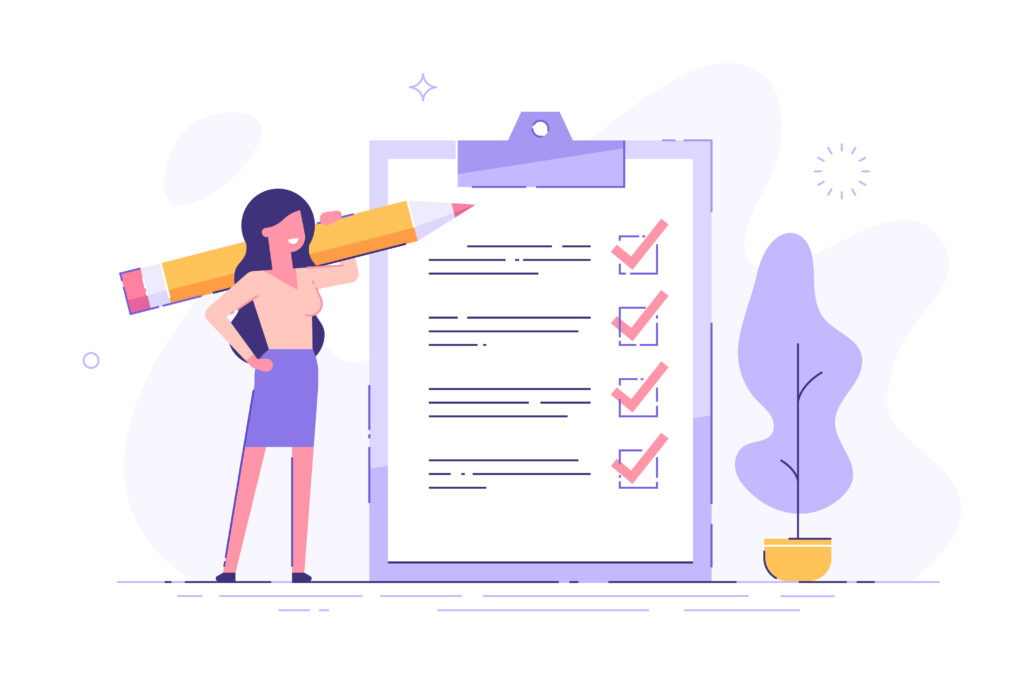
新しいサービスであるSBI e-iDeCoには、特に投資初心者にとって嬉しいメリットが多くあります。
1. 業界最安水準!運営管理手数料が誰でも0円
前述の通り、掛金の額や資産残高にかかわらず、SBI証券に支払う運営管理手数料が0円です。iDeCoは数十年という長期にわたる運用のため、わずかな手数料の差が将来の受取額に大きく影響します。このコストを完全に抑えられる点は、最大のメリットと言えるでしょう。
2. 投資初心者でも迷わない!厳選された低コスト商品
SBI e-iDeCoで選べる商品は、いずれも信託報酬(投資信託の保有コスト)が非常に低い、人気のインデックスファンドです。投資の基本である「長期・積立・分散」を手軽に実践できる商品が厳選されているため、知識に自信がない方でも安心して選べます。
3. スマホで完結!最短5分で申し込み可能
従来のiDeCoの申し込みは、Webで入力した後に書類を印刷して郵送するなど、手間と時間がかかるのが一般的でした。SBI e-iDeCoでは、これらの手続きがすべてスマホ上で完結し、入力項目もシンプルになっているため、思い立った時にすぐ申し込める手軽さを実現しています。
4. シンプルで分かりやすい専用アプリ
SBI e-iDeCoには専用のスマホアプリが用意されています。このアプリを使えば、現在の資産状況や運用損益の確認、掛金の配分変更などが直感的な操作で行えます。複雑な機能が削ぎ落とされているため、初心者でも迷わず使えるのが特徴です。
5. 引き落とし手数料も無料
毎月の掛金を引き落とす際の金融機関の手数料も無料です。運営管理手数料と合わせて、運用にかかるコストを徹底的に抑えられます。
知っておきたいSBI e-iDeCoの2つのデメリット・注意点

多くのメリットがある一方で、加入前に知っておくべき注意点も存在します。
1. 商品ラインナップが少ないと感じる可能性がある
投資初心者にとってはメリットである「厳選された商品ラインナップ」ですが、投資に慣れている方や、自分でさまざまな商品を組み合わせて積極的に運用したい方にとっては、選択肢が少ないと感じる可能性があります。より多くの商品から選びたい場合は、従来のセレクトプランの方が適しているでしょう。
2. iDeCo共通の注意点(60歳まで引き出せない等)
これはSBI e-iDeCoに限った話ではありませんが、iDeCoは老後資金の形成を目的とした制度のため、原則として60歳になるまで資産を引き出せません。急にお金が必要になった場合でも、iDeCoの資産は使えないのです。そのため、iDeCoに拠出する掛金は、当面の生活に影響のない余裕資金の範囲で設定することが重要です。
また、iDeCoの口座を維持するためには、金融機関に支払う手数料とは別に、国民年金基金連合会などに支払う手数料が最低でも合計で月額171円(年間2,052円)かかります。これはどの金融機関でiDeCoに加入しても発生する費用です。
SBI e-iDeCoの手数料を他の金融機関と比較

SBI e-iDeCoの運営管理手数料0円は、他の金融機関と比較してどれほど優位性があるのでしょうか。
主要ネット証券(楽天証券・マネックス証券)との比較
| 金融機関 | 運営管理手数料 |
| SBI証券 | 0円 |
| 楽天証券 | 0円 |
| マネックス証券 | 0円 |
このように、主要なネット証券では運営管理手数料を0円に設定しているのが現在のスタンダードです。SBI e-iDeCoは、手数料面で他のネット証券と肩を並べた、業界最安水準のサービスと言えます。
手数料で金融機関を選ぶ際の注意点
多くのネット証券が運営管理手数料を無料にしているため、金融機関選びでは「商品ラインナップ」や「サービスの使いやすさ」がより重要な判断基準になります。
SBI e-iDeCoは、商品数をあえて絞り、スマホでの使いやすさを徹底的に追求することで、他のネット証券との差別化を図っています。手数料だけでなく、これらのサービス面が自分の投資スタイルに合っているかを確認することが大切です。
SBI e-iDeCoのおすすめ商品2選【初心者向け】
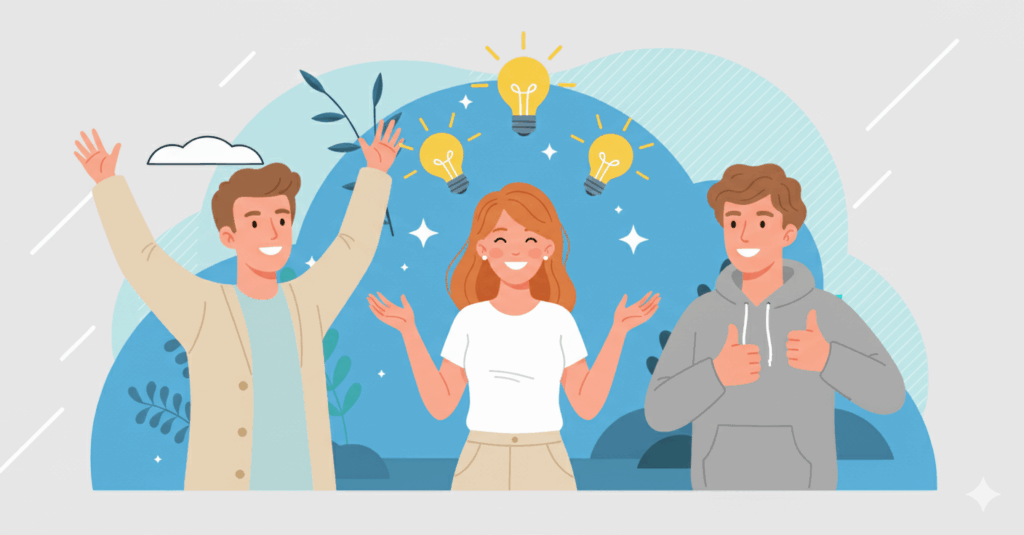
SBI e-iDeCoの厳選された3つの商品ラインナップの中から、特に初心者におすすめの2本を紹介します。
1. eMAXIS Slim S&P500
米国の代表的な株価指数である「S&P500」との連動を目指す投資信託です。アップルやマイクロソフトといった世界的な大企業約500社に分散投資する効果があり、長期的な成長が期待できます。信託報酬も極めて低く、これ一本で米国経済全体の成長の恩恵を受けることを目指せます。
2. eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
日本を除く先進国および新興国の株式市場全体に、これ一本で国際分散投資ができる投資信託です。「オルカン」の愛称で知られ、世界経済の成長をまるごと享受することを目指す商品として、NISAなどでも絶大な人気を誇ります。何に投資すれば良いか分からないという方が、最初に選ぶ一本として最適です。
【スマホで簡単】SBI e-iDeCoの始め方5ステップ

SBI e-iDeCoの申し込みは非常にシンプルです。ここでは、具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:公式サイトへアクセス
まずはSBI e-iDeCoの公式サイトにスマホからアクセスし、「口座開設」ボタンをタップします。
ステップ2:メールアドレス登録と必要事項の入力
画面の指示に従い、メールアドレスを登録します。その後、送られてくるメールのリンクから、氏名、住所、生年月日、基礎年金番号などの必要事項を入力します。基礎年金番号は、年金手帳や毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で確認できますので、事前に準備しておくとスムーズです。
ステップ3:本人確認書類の提出
運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を、スマホのカメラで撮影してアップロードします。郵送の手間がなく、その場で提出が完了するのが便利な点です。
ステップ4:掛金と運用商品の設定
毎月の掛金の金額(最低5,000円から)と、どの商品に何パーセントずつ投資するかの配分を設定します。おすすめ商品などを参考に、自分のリスク許容度に合った配分を決めましょう。
ステップ5:審査完了後、運用開始
申し込み内容に基づき、国民年金基金連合会などで加入資格の審査が行われます。審査には1〜2ヶ月程度かかります。審査が完了するとIDとパスワードが記載された書類が届き、専用アプリにログインして運用を始められます。
SBI e-iDeCoに関するよくある質問

Q1. 従来のプラン(セレクトプラン)からe-iDeCoに変更できますか?
はい、可能です。SBI証券のiDeCo加入者向けサイトから、プラン変更の手続きを行えます。ただし、プラン変更には一定の時間がかかる場合や、手続き中の取引に制限がかかる可能性があるため、詳細は公式サイトでご確認ください。
Q2. 会社員だけでなく、自営業者や主婦(主夫)も加入できますか?
はい、加入できます。iDeCoは20歳以上65歳未満の国民年金被保険者であれば、職業にかかわらずほとんどの方が加入できます。ただし、職業によって毎月の掛金の上限額が異なりますので注意が必要です。
Q3. 毎月の掛金はいくらから設定できますか?
月々5,000円から、1,000円単位で設定できます。年に1回、掛金の金額を変更することも可能です。無理のない範囲で始め、家計に余裕ができたら増額を検討するのが良いでしょう。
Q4. 転職した場合、何か手続きは必要ですか?
転職先の企業に企業型DC(企業型確定拠出年金)があるかどうかで手続きが変わります。転職先に企業型DCがない場合は、会社員としての登録情報の変更手続きが必要です。企業型DCがある場合は、iDeCoの資産を移換することも可能です。詳細はSBI証券のサポートにご確認ください。
【まとめ】スマホ世代の資産形成は「SBI e-iDeCo」から始めよう

この記事では、2025年10月に新しく始まったSBI証券の「SBI e-iDeCo」について、従来のプランとの違いやメリット・デメリットを詳しく解説しました。
最後に、重要なポイントを振り返ります。
- SBI e-iDeCoは、手数料・商品・手続きの3つの面で投資初心者に最適化された新サービス
- 運営管理手数料が誰でも0円で、コストを最小限に抑えられる
- 商品は人気の低コストファンドに厳選されており、迷わず始められる
- 申し込みから管理までスマホで完結し、圧倒的に手軽
老後のための資産形成は、早く始めるほど有利になります。「SBI e-iDeCo」は、これまでiDeCoにハードルの高さを感じていた方が、その第一歩を踏み出すための最適なツールです。
この記事を参考に、ぜひスマホから手軽に始められるiDeCoで、将来に向けた賢い資産づくりをスタートさせてみてはいかがでしょうか。
関連記事
SBI証券のiDeCo口座の開設方法を解説!商品ラインナップやおすすめの銘柄を初めての方にもわかりやすく紹介
SBI証券の口座開設ガイド!初めての方にもわかりやすく開設方法を詳しく解説!
OliveでSBI証券のクレカ積立を利用する方法を解説!手順からメリットやデメリットを紹介!
三井住友銀行のOliveとは?メリットや開設方法を紹介!お得なキャンペーンも実施中!
Oliveフレキシブルペイゴールドのメリットとその使い方を紹介!
Oliveフレキシブルペイの審査は厳しい?審査基準や審査にかかる時間を解説!
【2025年最新】Oliveキャンペーン完全ガイド!見逃し厳禁のお得情報と攻略法を徹底解説
【2025年版】Oliveと三井住友カード(NL)の違いを徹底比較!結局どっちがお得?
三井住友カードの完全ガイド!おすすめカード8選を紹介!カード利用のメリット・デメリットも解説




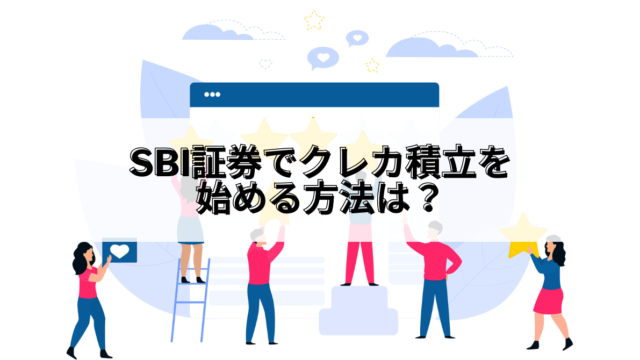


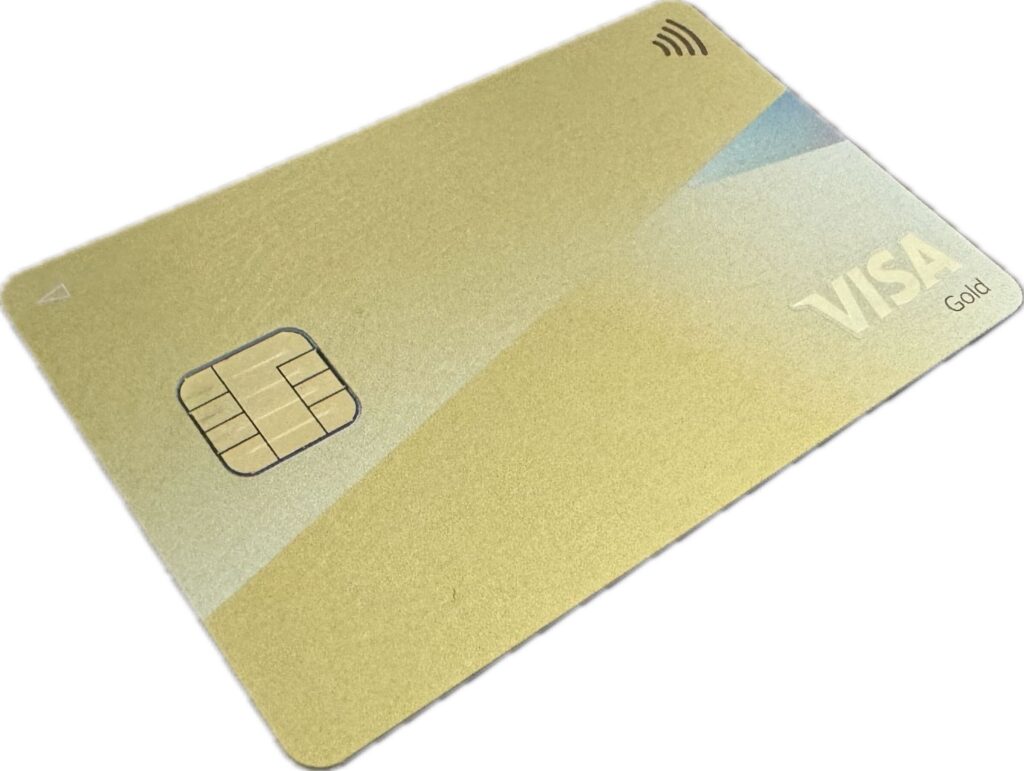

 OliveのANAマイル還元率は?ANAカードとの併用や最大12%還元の活用術を解説!
OliveのANAマイル還元率は?ANAカードとの併用や最大12%還元の活用術を解説!  【12月最新まとめ】Oliveキャンペーンで最大43,500円相当のVポイント獲得手順を解説!
【12月最新まとめ】Oliveキャンペーンで最大43,500円相当のVポイント獲得手順を解説!  【12月最新】Oliveの紹介コードはどこで入手できる?紹介特典や使い方を解説!
【12月最新】Oliveの紹介コードはどこで入手できる?紹介特典や使い方を解説!